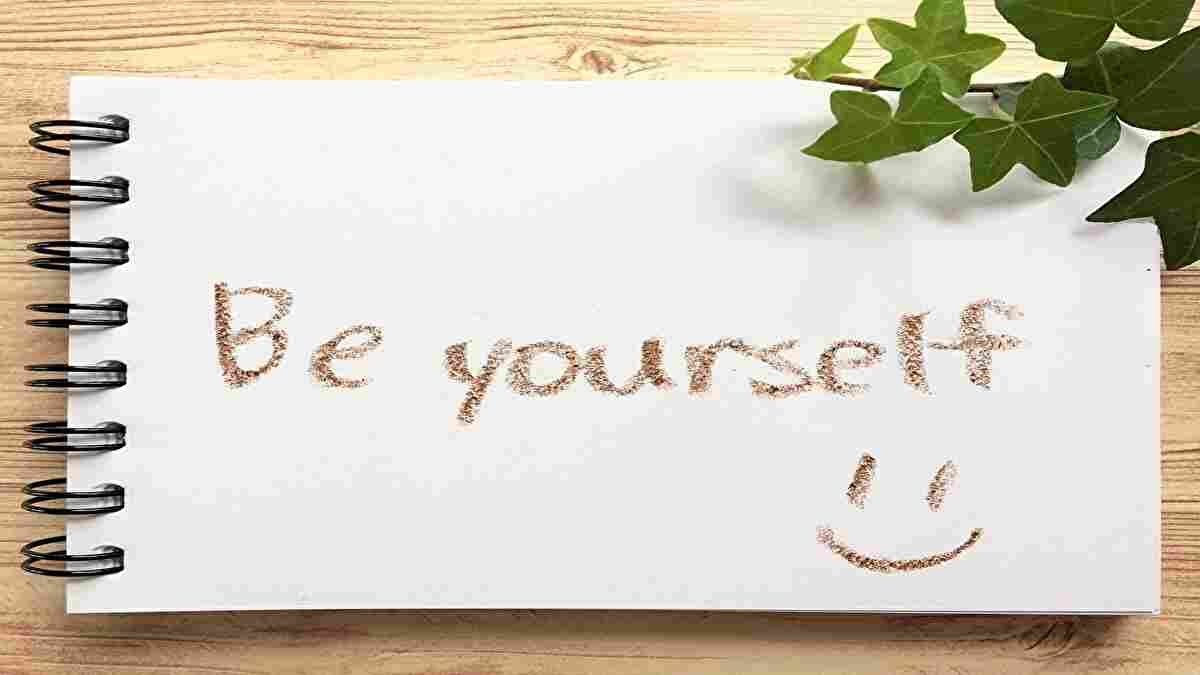自己分析の必要性を理解していない薬剤師、多いです。
そんなことしなくても就職できるよね。薬剤師資格あるんだし。
就職先選びは人生のターニングポイントになります。そんな重要な意思決定を自分のこともわからずに決めることはできません。
新卒者の就職先選びだけでなく、転職活動中の薬剤師も是非、自己分析して自分に合った仕事を見つけましょう。
薬剤師や薬学生の方は自己分析が不足しやすいです。
これは薬剤師資格によって就職先が一気に絞られるからだと思います。
普通の大学生、例えば経済学部の学生だったとしたら、就職を考えたときに自己分析せずには選べません。
なぜなら、あらゆる業界業種が就職先候補だからです。
ただ、薬学生の就職活動、薬剤師の転職活動に自己分析は必須です。
この記事の想定読者:薬学生だけど、しっかり自己分析したい方、薬剤師で転職活動中の方
この記事を読んで、自己分析についてしっかり理解して、さらには「自己分析→ガクチカ」 の流れを理解することにより就活を決定的に有利に進めるようになります。
就職活動は大切にしてください。人生の中でもかなり大きなターニングポイントになります。
Contents
なぜ薬剤師、薬学生の自己分析やガクチカは不足するか

自分がどんな特徴、考え方を持っていて、得意なことや苦手なことは何か。
自分にはどんな仕事内容が向いているのか?集団生活が得意か?それとも独りで黙々と作業 が向いているか?
自己分析して、自分自身の事をしっかり理解してからでないと就職先候補すら選べません。
ところが薬学生、薬剤師にはこのステップが無いのです。
多くの薬学生の就職活動は病院、薬局、ドラッグ、メーカーMR、進学の5択を消去法で選んで、生涯年収や初任給、あてにならない口コミでただなんとなく・・・・
でも、就職して3年もたたずに「こんなはずじゃなかった・・・」と転職活動です。
それからやっと転職活動の際に、本当に自分にあった職場を探して自己分析に取り組む方もいますが、それなら就活時点から取り組めばよいと思います。
薬学部生でも、文系学生と同じようにしっかり自己分析するべきです。
薬剤師のための自己分析の基本

薬剤師にとって自己分析とは
薬剤師にとって自己分析とはなんでしょうか。
いや、だれにとっても、自己分析とはまさに、自分を知ることです。
自分の事だから、もちろん、知っている。というのは、大きな勘違いで、みんな自分で自分の事がわかっていません。私もわかっていませんし、あなたもそうです。
分かっていないからこそ、自己分析手法を用いて自分で自分を知る必要があります。
自分の事を知って初めて、長期的なキャリアプラン、人生プランを立てることができます。
逆に言えば、場当たり的な転職を繰り返す薬剤師は自分の事がわかっていません。
転職先を探す時も「年収や休みの多さ」といった表面的な事柄でしか職場選びができないため、同じように次の職場でも満足度は低く、さらなる転職活動を繰り返すことになります。
薬剤師に自己分析が役立つ理由、メリット

薬剤師に自己分析が役立つ理由、メリットは多いですが、主に次の二つに集約されます。
- 自分に適した職種、職場がわかる
- 在職中の仕事に対するモチベーションが上がる
自己分析で自分に適した職種、職場がわかる
自己分析により自分に適した職種や職場がわかるようになります。
これが就職活動で自己分析が求められる理由です。
同じ人間でもカレーが好きな人とラーメンが好きな人がいるように、同じ薬剤師でも薬局向きの人と病院向きの人がいます。
単純に初任給が高いからとか、医師のカルテが見れるからといった、よく言われる理由だけでなく、本当に自分にあった職場として選ぶことができるようになります。
自己分析すると在職中の仕事に対するモチベーションがあがる
自己分析により在職中の仕事に対するモチベーションが上がります。
自分に適した職種を選んでいるうえ、納得して職業を選択しているので、仕事中の満足度も高まります。自分がなぜこの職場を選んでいるか、明確な基準を持っているので迷いません。逆に言えば、明確な基準を持たずに年収や休日、有給休暇の取りやすさ等、ありふれた基準だけで職場を選べば、何か嫌なこと、ストレスを感じたときに容易に転職という選択肢が出てきます。
自己分析するかしないか、ほんの少しの違いです。
ただ、人生の分岐点においては、ほんの少しの違いが振り返ってみれば大きな違いとなります。
よく大人が口にする「もうちょっと勉強してたらなぁ・・・」なんかまさにそれで、若い頃の少しの努力不足を一生後悔している人は多いです。
いつ自己分析するべきか

自己分析するタイミングは複数あります。もちろん、就活中は重要なタイミングの一つですが、もし自己分析したことない方は、いつでもいいので早いうちに一度はしてみてください。自分では気づいていなかった自分の特徴や思い込みなど、明らかにするだけで、現状に対する満足感は変わりますし、もしかしたらより良い転職のきっかけになるかもしれません。
誰と自己分析するべきか
自己分析は基本的に一人でする作業なので、誰とも一緒にする必要はありません。(ただし、一部の自己分析手法は他者へのヒアリングがあります)
もし、誰かと一緒に自己分析するとしたら、分析結果を共有すると良いでしょう。
友人との共通の話題とすることで、振り返るきっかけが増えますし、自分の中での意識付けも強くなります。
おススメの自己分析の方法
本屋に行けば自己分析に関する書籍はそれこそ山のようにあるので、自分の感覚で2,3冊購入すればよいと思います。
恐らく似たような内容ですが、結局やるべきことは実際に分析すること。
つまり読んで「ふ~ん」で終わりではなく、自己分析の実行です。
私が利用したのはたまたま読んだ「メモの魔力 The Magic of Memos (NewsPicks Book)」前田裕二著の付録にあった自己分析1000問です。
結構時間はかかりますが、自分自身と向き合う貴重な時間なので、むしろ長い時間がかかることにこそ価値があるはずです。ちなみに当時の私のメモには自己分析の結果として下記のようにありました。
君は社会に強さを認められると、他人の良い点に気付き、弱者の味方になれるんだね。でも新しい環境に入った直後は強さを示して来なかったから、認められてないと感じ、他人の悪いところに目がいってしまう癖があるよ!社会に認められる力をつけること、それを示すアイテムやタイトルを身に付けることは、君があるべき自分でいるために必要なこと。性格に合わなくても取り組むべきだね!
2019年2月5日著者メモ(Google Keep)
なんで自分に向かって「君は」とか詩的な呼びかけ方をしているのかは大いに疑問ですが、自己分析で自分再発見してテンション上がったからだったと思います。
ただ、結構読み返してみても今の自分に役立っていると実感します。
どんなときにどんな理由でストレスを感じやすいか、それを防ぐにはどう振舞えば(演じれば)よいかについて、答えてくれていると思います。
ちなみに私はブランドや肩書が大嫌いですが、自己分析の結果を受けて高級車を買って通勤することにしましたし、名刺の肩書はでかでかと「社長」といれました。
↑ここが結構、ポイントなんです。自己分析がないと「自分はブランドや肩書が嫌い」で終わってしまいます。
ただ、上記自己分析の結果で、自分は周囲に強さを示すようなアイテムやタイトルがあると、自分らしくいられる事が気付きでした。
なので、自分の趣味に合わない(と思い込んでいる)タイトルやアイテムをわざと生活に取り入れているんです。
自分の感性からすれば、少し違和感ありますが、それでもやってよかったと思っています。
ここまで読んで、転職しようと思った方は以下の記事「もう流されない!転職に迷う薬剤師が決めなきゃいけない3つのこと」もご参照ください。
もう流されない!転職に迷う薬剤師が決めなきゃいけない3つのこと
薬剤師(薬学生)の為の自己分析→ガクチカのススメ
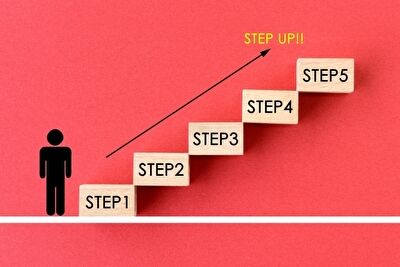
ここまでは薬剤師の為の自己分析について書きましたが、最後に就活中の薬学生のために、自己分析からのガクチカの作り方について書きます。
ガクチカとは
ガクチカは皆さんご存じの通り「学生時代に力を入れたこと」として、エントリーシートや面接でよく問われることです。
ガクチカは学生である皆さんが、その会社に入った後にどんな会社員になるかを推し量るために、採用企業側は聞いています。
就活時の提出資料の記載事項としては、かなり重要な項目となりますのでしっかりとした内容を記載したいところです。
ガクチカは一般的な就活生にとっては必須項目です。(薬学生にとってはそれほどですが)
大切なことは「ガクチカ作り」に走らないこと。
就活でガクチカが大切だから、ガクチカになるような活動をしなくてはならない、こんな思い込みをしている方が多いです。
そのため、ボランティアや海外協力、インターンや学内起業などなど、それっぽい事をする人がいます。
もちろん、本当にやりたくてやってるなら、ガクチカ関係なくOKですが、ガクチカ作りのためにはしない方がよいでしょう。
人は適材適所、自分を正しく表していないガクチカで、例え就活が上手く行ったとしても、それはあなたの適性にあった場所とは言えません。
就職前に外から見ている企業の姿など、ほんっっっの一部にしかすぎません。あなたが就職を熱望している企業では、まさに今「早く辞めてぇ、こんな会社」と思っている人がいます。
企業側に適性を見てもらうという意味でも、自分らしいガクチカとしましょう。
印象の悪いガクチカとは
採用側の意図が理解できていないと、印象の悪いガクチカになります。企業側は学生の人物像が知りたくてガクチカを聞いています。
単純に学生時代を振り返り、多くの時間を費やしたこと(部活やサークル活動)を思い浮かべ、思い出に浸ると、自分の印象に残っている事(大会で優勝したこととか、合宿行って楽しかったこと)をガクチカに書き連ねることになります。
印象の良いガクチカは自己分析をおさえている
採用側の意図をしっかり理解して、印象の良いガクチカを作成しましょう。
ガクチカの元となる材料は印象の悪いガクチカの項目で紹介したもの(部活やサークルの出来事など)と変わりません。ただし、多くの材料の中から、必要なものを取捨選別し、そこに自分自身の考えや気づき、学びといった記述を加えることで、グッと印象はよくなります。その際に、自己分析が欠かせないのです。
自己分析からガクチカを作成する
自己分析によって自分自身の特徴、特性が見えてきます。例えば、私の場合なら「タイトルを毛嫌いしているくせに、タイトルがあるとストレスが軽減されて仕事がスムーズにいく」という自己分析が出ています。これをガクチカのストーリーに落とし込みます。
(ガクチカの材料 例)
- バレー部に入部
- 部活内で仲が悪くなり、つまらない新人時代
- 2年生になってからは部活を楽しめた
(自己分析をストーリーに落とし込んだガクチカ 例)
「バレー部に入部したての頃は、先輩の指示にイチイチ噛みつく生意気な新人でした。でも、いつの間にか、周囲との摩擦が生じて部活の面白さが半減しました。ただ、続けていくうちにいつの間にか自分も先輩となり、後輩を指導する立場に。生意気だった自分を反省しながら、部を運営していくことにも面白さを感じ、どんどん部活が好きになっていきました。」
上記のようなガクチカ(実際には長さや表現など体裁は整える必要あり)を読んだ採用担当者は以下のように考えると思います。
「この学生はつまらない、と初めは感じることも継続することができ、継続することで状況が好転することを体験している。また、全体運営にも向いていそうだ。」
本当にこの通り、捉えてくれるかはわかりませんが、上記のようなガクチカは好印象なのは間違いありません。
大切なのは出来事を無作為に羅列するのではなく、ストーリーを持たせること。そのためには自己分析をしっかりして、自分に対する理解を深めなければ、ストーリーは描けません。
薬剤師に自己分析が必要だと感じましたか?

最後までこの記事を読んで頂きありがとうございました。
薬剤師にとって自己分析が必要であると感じていただけましたでしょうか。
ともすれば簡単に就職できる資格を持っているが故に、自分の適性を考える機会を失っている。
そんな多くの薬剤師の方が一人でも多く自分の事を知って頂き、より自分に適した職業を手に入れることを願っています。
自己分析とは何か──内面を掘り下げる力が未来を変える
自己分析とは、自分自身の性格・価値観・強みや弱み・過去の経験などを深く理解し、将来の意思決定や行動に活かすためのプロセスです。就職活動や転職、キャリアの見直し、人生の転機において不可欠なステップとして注目されていますが、その意義は一時的な活動にとどまりません。自分自身との対話を通して、本質的な欲求や目標を知り、より納得感のある生き方を見出す手段としても重要です。
自己分析の目的
自己分析の最も大きな目的は、「自分を理解し、より良い選択をすること」です。特に就職活動やキャリア形成の場面では、「自分は何をしたいのか」「どんな仕事が向いているのか」「なぜその会社や職種を選ぶのか」といった問いに対して説得力のある答えが求められます。その答えは、他人が与えてくれるものではなく、自分の内面を丁寧に掘り下げることによってのみ見出せます。
また、自己分析を通して得られるのは「自分に対する納得感」です。他人と比較して生じる焦りや不安は、自己理解が浅いと強くなりますが、自己分析によって「自分は自分でよい」という感覚を持てれば、より安定した自己肯定感が得られます。
自己分析の方法
自己分析には様々な手法がありますが、代表的なものをいくつか紹介します。
1. モチベーショングラフ
自分の人生の中で印象に残っている出来事を時系列で整理し、それぞれの場面での気持ちの高まりや落ち込みをグラフ化します。これにより、自分がどんなときにやる気が出るのか、どんな環境や出来事に弱いのかが視覚的に分かります。
2. 自己棚卸し(過去の経験の振り返り)
学生時代、アルバイト、部活、趣味、家族との関係など、人生における様々なエピソードを振り返り、それぞれの中で「自分が大切にしていたこと」「どのように行動したか」「結果はどうだったか」を掘り下げていきます。自分の価値観や行動パターンを見つけるのに有効です。
3. 他者からのフィードバック
自己分析は主観的になりがちなので、家族や友人、同僚からの意見も参考にすることで、新たな気づきを得られることがあります。自分では気づかなかった長所や短所が浮かび上がることもあります。
4. 診断ツールの活用
最近では、性格診断(MBTI、エニアグラム、ストレングスファインダーなど)やキャリア診断ツールを活用する人も増えています。これらはあくまで補助的なものですが、客観的な視点から自分を知る手がかりになります。
自己分析のメリット
・説得力のある自己PRができる
面接や履歴書で「自分はこういう人間です」と伝えるとき、自己分析ができていれば、具体的なエピソードや一貫性のあるメッセージを伝えることができます。これにより、信頼感や納得感が生まれます。
・ミスマッチを防げる
自己分析が不十分なまま就職や転職をすると、「想像していた仕事と違う」「価値観が合わない」といったミスマッチが起こりやすくなります。逆に自己理解が深ければ、企業や職種を選ぶ際の判断基準が明確になり、長期的な満足度が高まります。
・人生の方向性が定まる
自己分析は、職業選択だけでなく、人生そのものの軸をつくる作業でもあります。何を大切にして生きたいのか、どのような暮らしが自分らしいのかといった問いに向き合うことで、日々の選択に自信を持てるようになります。
自己分析の注意点
自己分析は深めすぎると迷子になることもあります。「完璧に自分を理解してから動き出そう」と考えるのではなく、ある程度見えたところで行動を起こし、経験を通してさらに深めていく「行動と振り返りのサイクル」を意識することが大切です。
また、理想の自分ばかり追い求めて、現実の自分を否定してしまうのも避けたいところです。自己分析は「良い自分」だけでなく、「不完全な自分」も受け入れるプロセスです。
おわりに──自己分析は一生モノのスキル
自己分析は就活や転職のためだけの作業ではありません。ライフステージが変わるごとに、自分自身を見つめ直す機会は訪れます。そのたびに、より深く、より柔軟に自分を理解する力が求められます。
「自分とは何者か」を考えることは難しく、時に苦しい作業でもありますが、その先には「自分らしく生きる」という最大の報酬が待っています。自己分析は、人生という長い旅を進むための、最も信頼できるコンパスとなるのです。
ガクチカとは何か?──就職活動における意味と本質を理解する
「ガクチカ」という言葉は、「学生時代に力を入れたこと」の略語であり、就職活動における自己PRの定番項目として知られています。企業のエントリーシートや面接でほぼ必ず問われるため、就活生にとって避けては通れないテーマです。本記事では、ガクチカの意味や目的、企業が求めている本質、そして効果的な書き方について、詳しく解説します。
ガクチカとは?
ガクチカとは、「学生時代に力を入れたこと(学生時代に最も頑張ったこと)」の略語で、自己PRの一種です。サークル活動、アルバイト、学業、ボランティア、留学、起業など、ジャンルは問いません。重要なのは、その経験を通して自分が何を学び、どのように成長したのかを論理的に伝えることです。
企業がガクチカを聞く理由
多くの学生が似たような経歴(大学、サークル、アルバイトなど)を持っている中で、企業は「この人がどのように考え、行動し、成長してきたのか」を知ることで、その人の人柄や仕事への適性を判断しようとします。
企業がガクチカから見たいのは以下のような要素です:
- 課題発見能力:自ら問題点を見つけ出せるか
- 主体性・行動力:自分の意思で物事を進められるか
- 協調性・リーダーシップ:集団の中でどのような役割を果たせるか
- 継続力・粘り強さ:困難を乗り越えて努力できるか
- 成果とその過程:結果を出すために何をしたか
つまり、単に「何をやったか」ではなく、「どう取り組み、どう成長したか」が問われているのです。
ガクチカの内容は特別なものでなくてよい
よくある誤解として、「ガクチカには華やかで珍しい経験が必要」と思い込む就活生がいます。しかし、企業が重視しているのは「経験の中身」よりも、「取り組み方」や「姿勢」です。
たとえば、次のような例でも十分ガクチカになります:
- ファストフード店のアルバイトで接客マニュアルを改善した
- 体育会サークルで後輩育成の仕組みを構築した
- 大学のゼミでリーダーとして研究発表をまとめた
- 家庭の事情で働きながら学費を自力で賄った
どんな経験でも、自分なりに工夫し、試行錯誤し、乗り越えたことがあれば、それは立派なガクチカです。
ガクチカの構成:PREP法で論理的に伝える
ガクチカを語る際には、論理性が重要です。PREP法(Point→Reason→Example→Point)を使うと、わかりやすく筋道だった文章になります。
- 結論(Point):「学生時代に最も力を入れたのは◯◯です」
- 理由(Reason):「なぜそれに力を入れたのか」
- 具体例(Example):「どのように取り組み、どんな困難があり、どう乗り越えたか」
- まとめ(Point):「この経験から何を学び、それをどう活かしたいか」
以下に具体例を示します。
例:飲食店アルバイトのガクチカ
結論:私が学生時代に最も力を入れたのは、居酒屋でのアルバイトにおいて、業務改善を行った経験です。
理由:アルバイト先では注文ミスが頻発しており、スタッフの間でも不満が多く、何か改善できないかと考えたためです。
具体例:私はまずミスの原因を特定するために、1週間分のミス内容を記録・分析しました。その結果、注文時の聞き間違いや伝票の記載ミスが主因だとわかり、iPadによる注文管理の導入を提案。店長と協議の上、試験導入を行い、1か月後には注文ミスが半減しました。
まとめ:この経験を通して、課題発見から解決に向けた提案・実行の重要性を学びました。入社後も現場の声を拾い、改善に向けて主体的に行動したいと考えています。
ガクチカを書くときの注意点
- 結果だけでなく過程を重視すること
「◯◯大会で優勝した」といった成果だけでなく、「なぜ・どうやって」達成したかを具体的に書きましょう。 - 盛りすぎない・嘘はつかない
面接で深掘りされた際にボロが出ると信頼を失います。事実をもとに自分の成長を語ることが大切です。 - 1つに絞る必要はないが、焦点は明確に
複数の経験を語っても構いませんが、各経験の中で何を学び、それをどう活かすのか明確にしましょう。
まとめ:ガクチカは自分を映す鏡
ガクチカは、自分自身の価値観や思考、行動パターンを企業に伝える大切な材料です。「どんな経験をしたか」よりも、「その経験を通じてどう考え、どう成長したか」が問われています。
就職活動は自己分析と他己分析の連続です。ガクチカを通じて自分の軸を言語化し、相手に伝える練習を積むことは、選考だけでなく、入社後のキャリア形成にも大いに役立つでしょう。